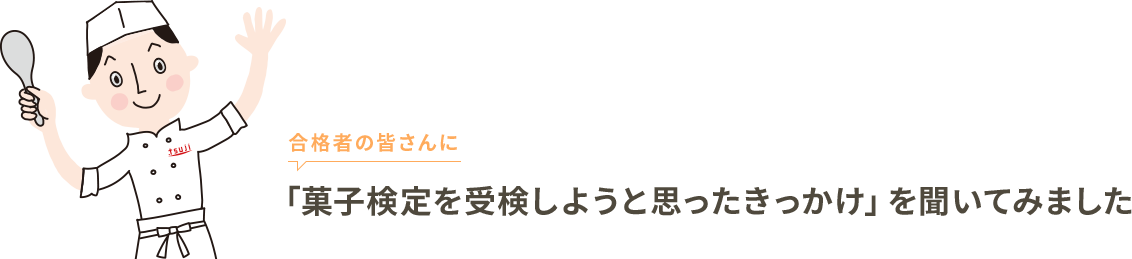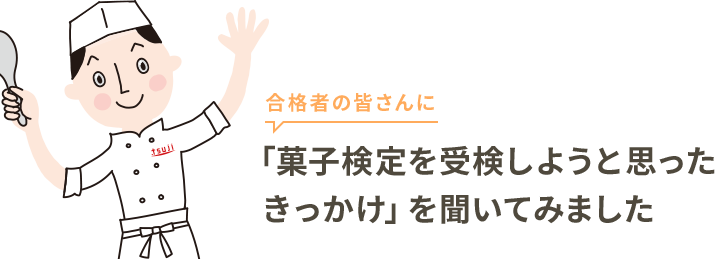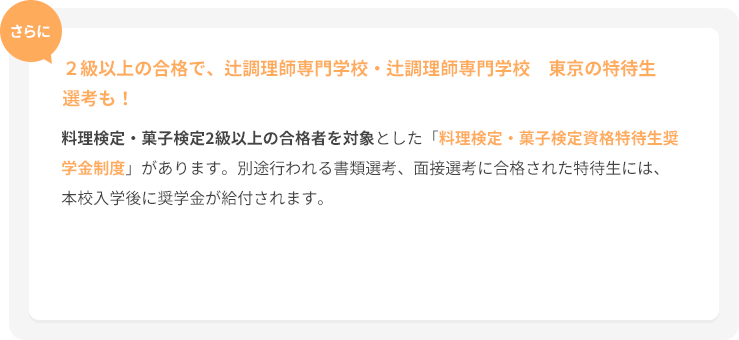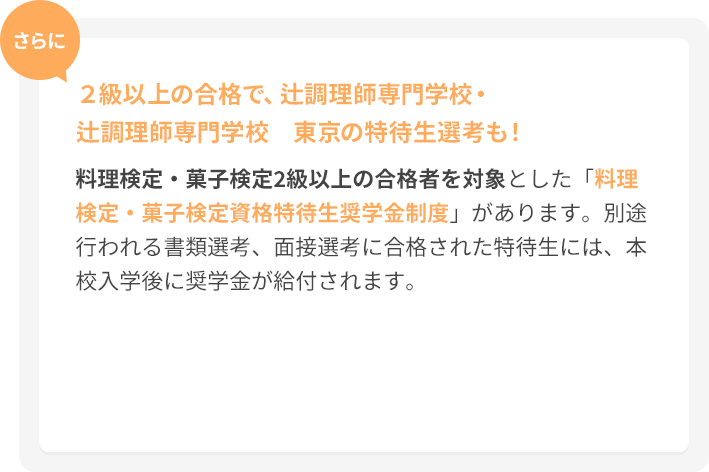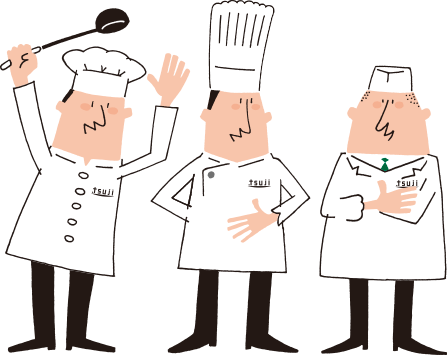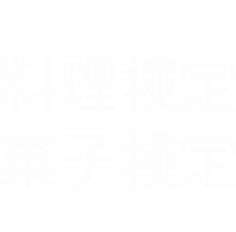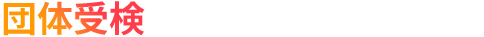料理検定・菓子検定総合サイト
料理検定・菓子検定総合サイト

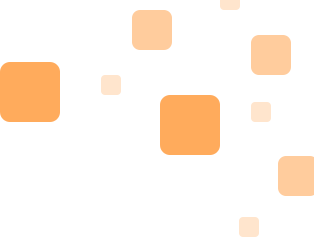
菓子検定とは
菓子検定は、お菓子の可能性を感じ、
もっとお菓子を楽しむ検定です。
菓子の食材、製菓法や道具、
さらに菓子文化についての知識を問います。
どんなお菓子にも歴史があり、
つくり方のコツがあります。
「見る、触る、聞く、嗅ぐ、味わう」
―五感を総動員してつくるのです。
数多くのプロのパティシエや和菓子職人を
育ててきた私たちは、お菓子が大好きな
あなたに、
あるいはプロを目指すあなたに、
もっとお菓子のことを
理解してほしい、
もっとおいしさを感じてもらいたいのです。
そんな思いから「菓子検定」は始まりました。

-
特に洋菓子を勉強する機会がなかったのでとても良い知識がついたと思います。和菓子では18年のキャリアですが、おはぎの別名「隣り知らず」という事など初めて知りました。まだ知らないことが沢山あり、改めて一生勉強だなぁと思いました。
千葉県 / 菓子製造販売業
-
2級は3級よりも和菓子の内容がより深く少し大変でしたが、その分よりためにもなり製造や接客時、少しでも生かせられたらと思います。
千葉県 / 自営業
-
テキストで勉強していると、その伝統のお菓子にお菓子職人さんのエッセンスが加えられ、伝承され進化していることを知り、より歴史的な背景にも深く興味をもつようになりました。
大阪府 / 事務職
-
受検動機は、昔からお菓子づくりが大好きでよくクレープやシフォンケーキを作っていました。高校生になって、スイーツコーナーに入り、色々なことを学んでいく内に、益々お菓子に興味を持ちました。そんな時にこの検定をネットで知り、受けてみようと思い、無事サクラサク!(笑)
東京都 / 高校生
各級の概要
プリンやクッキー、
おはぎなど。
成り立ちや種類を知って
なじみのお菓子を
もっとおいしく!
菓子検定3級はお菓子に興味を持つ人を広く対象にしています。
検定問題では、身近なお菓子について基本的な知識が問われます。洋菓子に関する問題が80~90%、和菓子に関する問題が10~20%。その他、栄養・衛生についての初歩的な問題が数%含まれます。
洋菓子部門
日本で親しまれている洋菓子と、西ヨーロッパと北アメリカの代表的なお菓子について出題します。
検定問題の中心は、プリンやショートケーキ、クッキーなど定番のお菓子がどのようなものか、その成り立ちや名前の由来、使われている生地・クリームは何かなどを問うものです。
お菓子のつくり方に関する初歩的な知識と、小麦粉、砂糖、卵、乳製品、果物など一般的な洋菓子の材料、よく使う器具の基礎知識についての問題もあります。
和菓子部門
和菓子の中で、特になじみの深いお菓子のつくり方や材料について出題します。
検定問題の中心は、柏餅・おはぎ・ようかん・カステラなどのお菓子のつくり方・材料・由来などについてです。どのような行事や節句に関係するのかといった、周辺知識に関わる問題もあります。また、米粉・葛粉・きな粉などの基本的な材料については、原料や種類に関する問題、基本的な器具については、使い方に関する問題などもあります。
食品衛生・栄養など
フランス菓子や
和菓子など。
器具や材料の特性を
生かしてとびきりの
おいしさに。
お菓子に深い関心を持つ人、家庭でお菓子を作っている人を対象にしています。一般的なものから専門性の高いものまで、幅広いお菓子の知識が問われます。洋菓子の問題がおよそ80%、和菓子の問題がおよそ20%。その他、栄養・衛生の初歩的な問題が数%含まれます。
洋菓子部門
フランス菓子を中心にヨーロッパの一般的なお菓子について出題します。お菓子の構成、語源や由来などが問題の中心です。また、洋菓子づくりの基礎になっているフランス菓子の基本生地とクリームについて、実際のレシピにそって材料、分量、つくり方の手順を答える問題があります。さらに基本的な製菓材料の歴史的背景と、それがお菓子をつくる過程でどのような働きをするかも問われます。3級に続いて一般的な材料、器具に関しても出題します。
和菓子部門
菓子の中で、専門性のあるお菓子について出題します。検定問題の中心は饅頭・上生菓子・餅菓子・団子などの作り方・材料・由来などについてです。お菓子の起源や変化の過程、歴史などについて、また、和菓子に使われる白玉粉・餅粉・上用粉・上新粉などさまざまな粉の性質や特徴についての問題もあります。一部、ぜんざい・かるかんなど地域性のあるお菓子や、日本茶についても取り上げて出題します。
食品衛生・栄養など
お菓子作りを
仕事にするために!
技術や知識の
向上だけでなく、
食の安全や
健康にも配慮
お菓子作りやお菓子に関わる仕事をしている、または目指している人、菓子作りの経験がある程度あり、さらに知識を深めて製菓技術を向上させたり、発想力を養ったりしたいと考えている人を対象にしています。
洋菓子、和菓子を問わず、製菓全般について2級、3級で学んだ内容をさらに深く学習・考察することが求められます。1級ではパンについての問題も加わります。
部門にとらわれることなく、菓子およびパンの種類や材料、器具、配合、製造工程について専門的な知識が問われます。さらに洋の東西を問わず、広い地域を対象に、菓子やパンの背景となる食文化や歴史の知識も必要とされます。製菓店の運営や販売、飲料の提供などに関する出題もあります。
食を扱う仕事に就く上で欠かせない食の安全や人の健康に関わる問題の比率も高くなります。
合格者特典

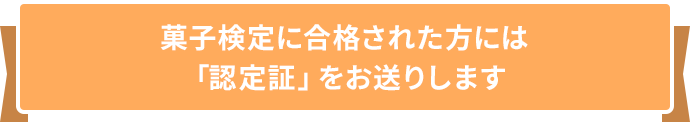
"La gastronomie ne cesse d'évoluer"
これは「美食は常に進化しづけるものである」
という意味のフランス語。
もっと深く料理やお菓子がもつすばらしさを知ってほしい、
これからも学び続けて欲しい
という私たちの思いでもあります。

合格者の皆さんへ認定証と共にお届けするのは、
検定を主催している辻調理師専門学校の
「別科 通信教育講座」の映像教材です。
菓子検定を通して身につけた
「知識」をさらに深めるとともに、
検定だけでは身につけることのできない
「技術」に触れる場になればと願っています。
特典映像
3級は「洋菓子技術講座 第1課」
2級は「洋菓子技術講座 第2課」「和菓子技術講座 第1課」
1級は「和菓子技術講座 第2課」「製パン技術講座 第1課&第2課」
※上記映像は各講座(全24課または全12課)の第1課と第2課に該当します。
※認定証の裏面のQRコードからご覧いただけます。